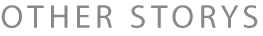ヒノキを植えられない土地に
漆を植えたのが始まり
曽爾村の塩井地区で生まれ育った松本さん。「漆ぬるべ会」の設立当初から関わり、現在は同会の2代目会長を務めていますが、関わる前は漆に興味はなく、塩井地区が漆の発祥の地だとは知らなかったそうです。「戦後、植林ブームが起こりましたが、塩井地区は土地がやせていて植林しても育たない。通常はヒノキであれば育つのに、やせ過ぎてヒノキすら植えられない土地が約40アールありました。そこを花屋のご主人が借りて販売用の松や槙を植えていましたが、2001年に亡くなり、塩井地区の歴史的背景から『漆を復活させよう』と決まったのです」。


繊細な植物である漆に
苦労ばかりの日々
翌年、松本さんは塩井地区の人たちと活動を始めます。「漆を植えるノウハウはまったくなかったので、岡山県の専門家を招いて漆の原木を探したところ、11本見つけました」。塩井地区の事業として漆の植林に取り組むアイデアも出たそうですが、高齢者には負担が大きいことから、有志で活動することに。こうして2005年に「漆ぬるべ会」が発足したのです。「苗づくり、植栽、鹿対策、草刈、作業道づくり、伐採など、重労働ばかりの活動で(笑)。2010年には1000本近く植えたのですが、土地がやせていて育たなかったり、獣害などもあり、今では30本ほどしか残っていません。漆は繊細な植物。苗を植え直したりして、かなり苦労しました」。

 2010年に植えた植栽地。
2010年に植えた植栽地。 失敗を元に2012年に植えた植栽地。大きく成長し漆の森となっている。
失敗を元に2012年に植えた植栽地。大きく成長し漆の森となっている。 集落を見下ろす見晴らしいの場所に、漆の森はあります。
集落を見下ろす見晴らしいの場所に、漆の森はあります。
日本古来の産物である漆を
みんなで大事にしたい
それでも松本さんたちはめげず、2012年に100本ほど植えました。現在、そのうちの半分が4〜5メートルに育っています。回を重ねるごとに土づくりや水はけなどの手法を改良し、2015年と2018年にもそれぞれ植えました。今松本さんは、村としての取り組みを喜び、期待しています。「日本古来の産物である漆をみんなで大事にし、数年後に全需要のうちのほんの数%でも曽爾村で漆が採れれば、『ぬるべの郷』として夢があるんじゃないかと思っています」。

漆の魅力を伝える活動の一環で、「ぬるべの郷漆工房」として採取した漆を使ってつくった、色も形もさまざまな柿の葉の器。